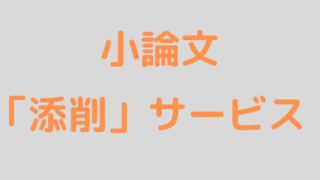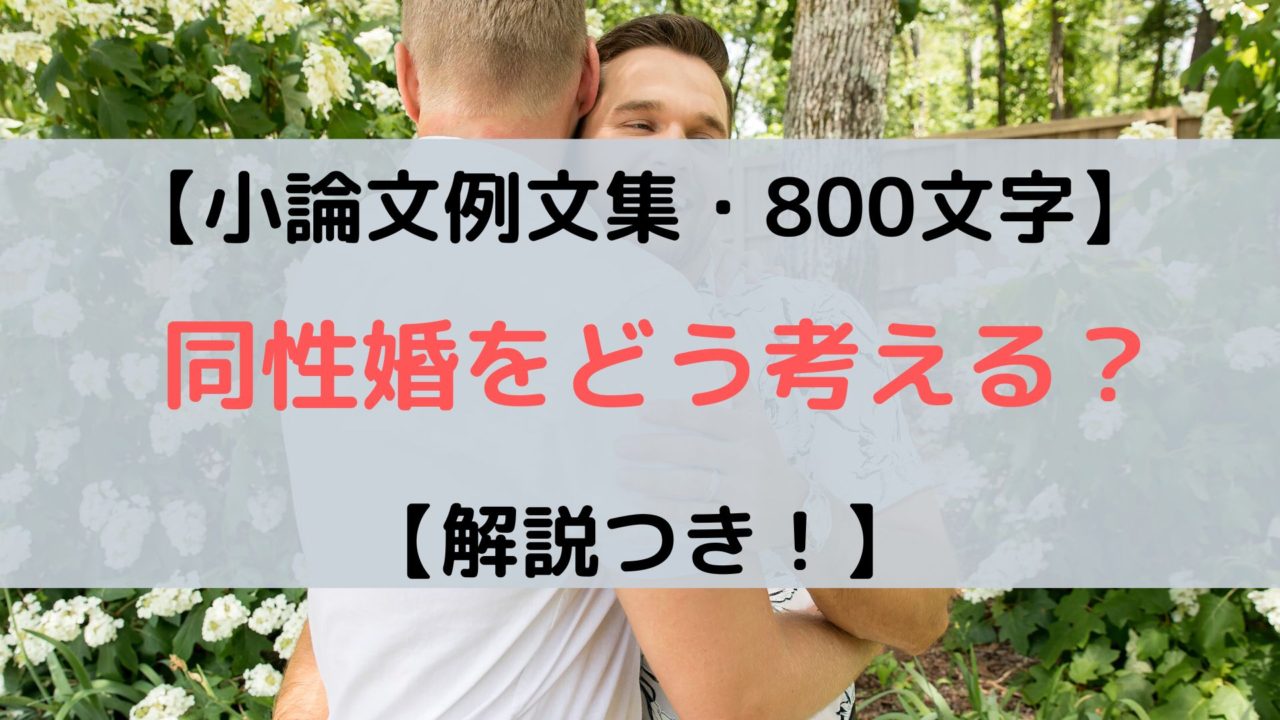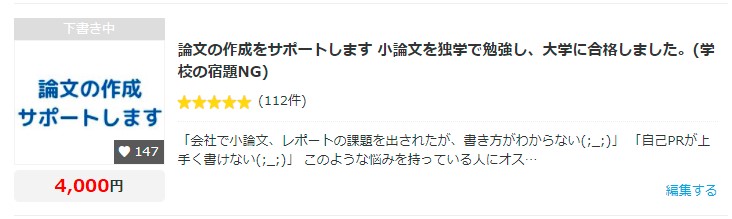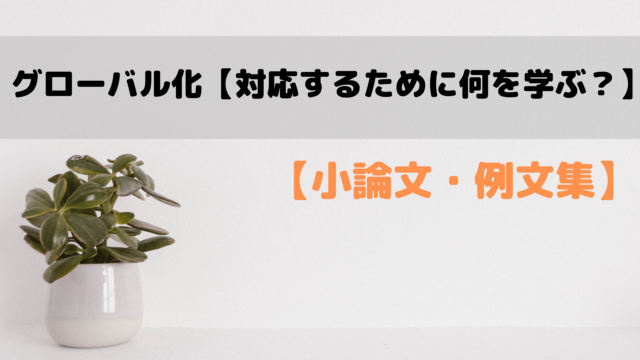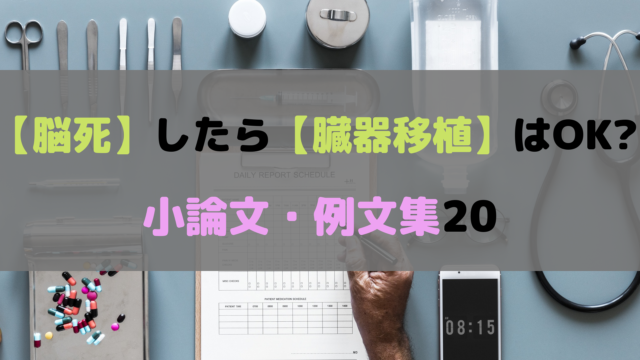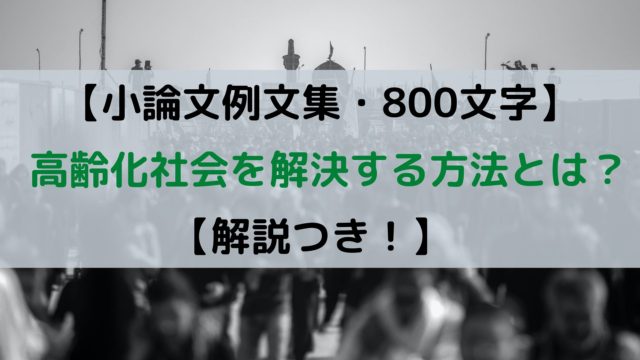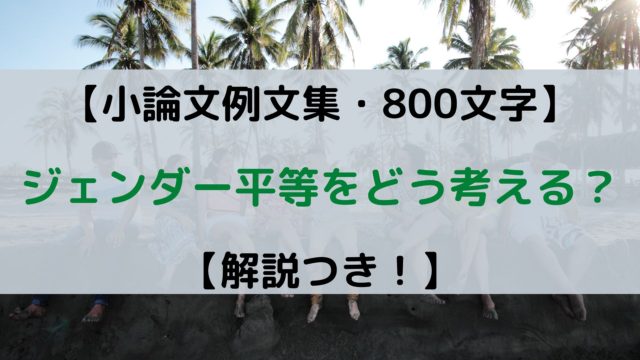この記事の内容は、YouTubeでも解説しています
この記事は、上のような悩みを持っている人に向けて書かれています。
では記事の詳細に入る前に、まずは軽く僕の自己紹介をさせてください。
- 小論文を使って大学に合格
- 小論文の書き方を教える当ブログを作成
- 小論文の添削を通じて大学合格者を輩出→小論文添削サービス
- 昇格試験論文のサポートをこなした経験あり→小論文サポートサービス
- 某省庁のエントリーシートのサポートをこなした経験あり→小論文サポートサービス
- 論文関連のYoutube動画を作成↓
今回は、以下のお題で考えていきます。
お題:度々報道されるニュースをキッカケとして、同性婚の問題が多く議論されるようになってきた。あなたは同性婚についてどのような意見を持っているか?800字程度でまとめなさい。


ここ最近、同性婚に関するニュースが増えてきた印象があります。
一昔前までは、同性を愛する気持ちは受け入れられない雰囲気がありました。ただ、多くの方のカミングアウトなどによって、「同性を愛する気持ちを持つ人はたくさんいるんだ」ということが明らかになってきました。そしてこの理解の向上に伴って、「なぜ同性婚が認められないんだ」という声が大きくなってきたように思います。
こういった注目度の高いテーマは取り上げられやすいので、この機会にしっかり考えておきましょう。
今回の記事では、まず同性婚に関するニュースやデータを整理していきます。自分の考えを書くには、多様な知識が必要になりますからね。
そして次に、ニュースやデータを踏まえた小論文を書いていきます。また、加えて小論文の書き方についても解説しますので、その解説もぜひ参考にしてください。
同性婚に関するニュースやデータの整理
ではまず、「同性婚は憲法レベルで認められていない?」というお話から見ていきます。
同性婚は憲法レベルで認められていない?
同性婚の話を議論する時、まず語られるのが日本国憲法の話です。
憲法24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」という記載があるんですね。
ポイントは「両性」「夫婦」という言葉です。これは「男」と「女」の異性同士を意味しており、同性婚は認められないという主張があります。ただ、この主張はあくまでも捉え方の問題であって、明確に同性婚が否定されているわけではありません。
とはいえ、結婚は「男」と「女」がするものという発想が一般的であり、そういった発想の元に世の中の仕組みや民法が整えられているのが実情です。
例えば民法第763条を見ても、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と記載されています。「夫婦」という表現が用いられていまして、やはりこれは「男」と「女」を意味していると考えるのが妥当です。
まとめると、「同性婚は憲法レベルで認められていないとは言えないが、仕組みや雰囲気を鑑みれば、同性婚が認められていないのが実態」と言えます。
同性婚が認めらないデメリット
同性婚の議論が巻き起こると、次のような主張をする人が必ず出てきます。
はい、一見その通りにも思えますが、実はこの主張は多くのデメリットを見逃しています。同性婚が認められないことには、以下のようなデメリットがあります。
- パートナーの遺産を相続できないケースがある
- パートナーが命の危機に瀕している時、そばにいられないケースがある
- 社会的に認められていないことで、常に精神的な苦痛がある
- 配偶者控除を受けられない等の金銭的な不利がある
はい、このように様々なデメリットがあることを押さえておきましょう。
パートナーシップ制度が解決策になる?
現状日本では同性婚は認められていませんが、同性婚に近い制度は存在しています。それは、「パートナーシップ制度」という制度です。
これは自治体が同性カップルに対して、「結婚に相当する関係」を認める証明書を発行する制度となっております。この証明書の発行によって、社会的な配慮が進むことが期待されています。
例えば先程デメリットとして、「パートナーが命の危機に瀕している時、そばに入れないケースがある」と説明しましたが、パートナーシップ制度によってこの問題が改善される可能性があります。面会を認めるか否かは病院の裁量に委ねられており、法律などで制限されているわけではありませんからね。
ただ、パートナーシップ制度で全ての問題が解決するわけではありません。婚姻が法的に認められるわけではないので、相続や配偶者控除等の問題は残り続けます。
パートナーシップ制度の利用者は何組いるのか?
では、パートナーシップ制度の利用者が現状どの程度いるのかも見ていきましょう。
渋谷区による全国パートナーシップ共同調査によると、2022年12月時点での交付件数は4186組となっております。
この数字だけを見ると、利用した人は1万人にも満たないことになりますが、これはあくまでもパートナーシップ制度を利用した人の人数にすぎません。同性が好きであることをカミングアウトできていない人はたくさんいるでしょうし、同性のパートナーがいてもパートナーシップ制度を利用していない人はいくらでもいるでしょう。
そう考えると、同性婚の問題に悩まされている方は、僕たちが想像している以上にいるのかもしれません。
では、ここまでの情報を踏まえて例文を書いていきます。例文の後には書き方の解説もつけますので、ぜひ参考にしてください。
例文
お題:度々報道されるニュースをキッカケとして、同性婚の問題が多く議論されるようになってきた。あなたは同性婚についてどのような意見を持っているか?800字程度でまとめなさい。
同性を愛する気持ちをカミングアウトする人が多数出てきたことなどに伴って、同性婚に関する議論も活発になってきた。現在の日本の法律では、異性同士の結婚しか認められていない。それゆえに、精神的な苦痛を味わったり、税金関係で不利益を被ったりする人が多数いるのが今の実態だ。この実態を改善するには、どのような対策が必要になるだろうか?
結論から言うと、パートナーシップ制度の利用を推し進めることが考えられる。なぜなら、当制度を利用することによって、ある程度改善できる部分があるからだ。例えば病院での面会に関して言うと、正式な夫婦ではないという理由で、同性パートナーが面会を断られてしまうケースがある。ただ、パートナーシップ制度によって発行された証明書を提示すれば、病院側が配慮してくれる可能性はある。したがって、よりパートナーシップ制度の利用を推し進めることで、同性婚の問題で悩む人の想いをある程度解消できると言えるだろう。
しかし、パートナーシップ制度で解消できる悩みは一部分にすぎず、利用を推し進めるだけで当問題が解決するわけではない。ただ、それでもパートナーシップ制度の利用を推し進めることには大きな意義がある。なぜなら、利用者数の増加に伴って、現状の仕組みや価値観が変化していくと期待できるからだ。どんな変革にも、ある程度の実数が必要だ。変革は少数派から起きるものだが、少数では起こせない。そう考えれば、まずは利用者数の増加に注力することで、変革のための力を蓄えることは理にかなっているだろう。
今回は同性婚の問題を踏まえた上で、パートナーシップ制度の利用を推し進めることを解決策として述べた。この解決策が同性婚の問題を根本から解決することはないが、変革を起こすための力にはなる。したがって、今は議論を深めつつも、パートナーシップ制度の利用を推し進めることに注力するべきだと私は考える。
【例文解説】


通読お疲れさまでした!
「パートナーシップ制度の利用を推し進めることが考えられる」という主張を軸に小論文を書いてみました!
この小論文は以下4つのブロックで構成されています。
- テーマ解説と問題提起
- 主張
- 主張に対する懸念点
- まとめ
それぞれのブロックを簡単に解説していきますね。
①テーマ解説と問題提起
テーマの解説+問題提起という王道の書き出しです。
サラッとテーマにまつわる話をした後に、問題を投げかければOKです!
非常に使い勝手がいいので、ぜひ身につけてください。
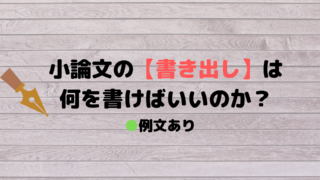
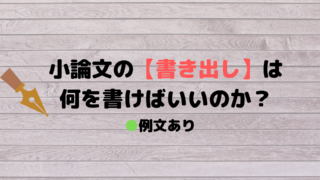
今回の場合で言えば、同性婚が認められていないことで生じる不利益を述べられれば十分です。
なぜなら、今回のお題が生まれた要因が「同性婚が認められていないことで困っています!」という声が大きくなってきたことにあるからです。
このように、お題の背景を想像すれば書くべきことは浮き彫りになります。
②主張
①の問題提起に対する主張をするという、オーソドックスな書き方です。
主張に加えて「理由」をいれたのがポイントです。
ただただ自分の主張を述べるだけでなく、その後に理由を入れることによって、説得力が増しますので覚えておきましょう。
- 主張→パートナーシップ制度の利用を推し進めることが考えられる
- 理由→当制度を利用することによって、ある程度改善できる部分があるから
③主張に対する懸念点
あえて自分の主張に対する懸念点を書くのは、小論文の鉄板テクニックです。
小論文が議論しているような形式になり、文章に深みが出ます。
しかし最後は、懸念点を解消して締めるようにしてください!
主張に対する懸念点だけ書いて終わってしまうと、悪い印象を与えたままになってしまいます。
それでは本末転倒ですからね。
- 主張に対する懸念点→パートナーシップ制度で解消できる悩みは一部分にすぎず、利用を推し進めるだけで当問題が解決するわけではない
- 懸念点の解消法→利用者数の増加に伴って、現状の仕組みや価値観が変化していくと期待できる
④まとめ
最後は今まで述べてきたことを表現を変えて短くしたり、論文を通じて強調しておきたいことなどを書いたりすればOKです。
テンプレとしては、②と③の重要な部分だけを抜き出して伝えれば十分でしょう。
まとめの書き方は、要約の手法を身につければ簡単に書けるようになります。
ぜひ下記のページを参考にしてください。
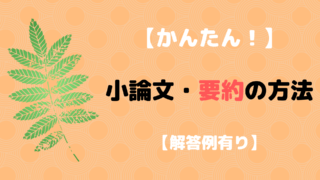
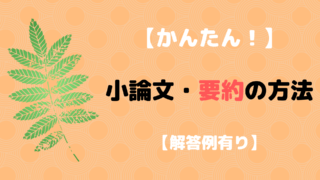
「他の例文からも学びたい!」という人は下記のページへ。


複数のお題から学ぶことであなたの小論文の幅が広がり、どんなテーマにも対応できる力が身につきます。
また、今回の例文は以下のページの構成を使用しています。
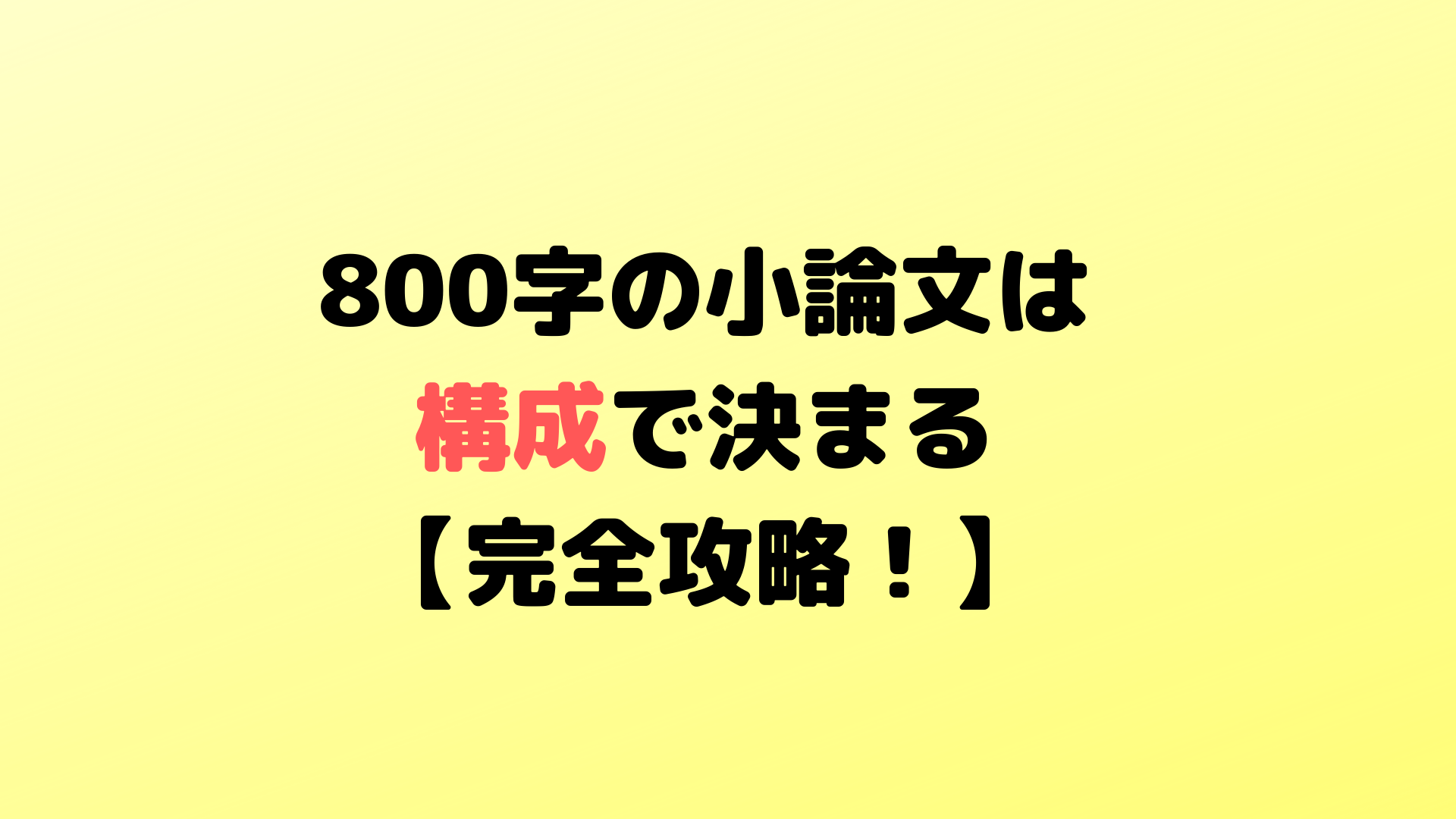
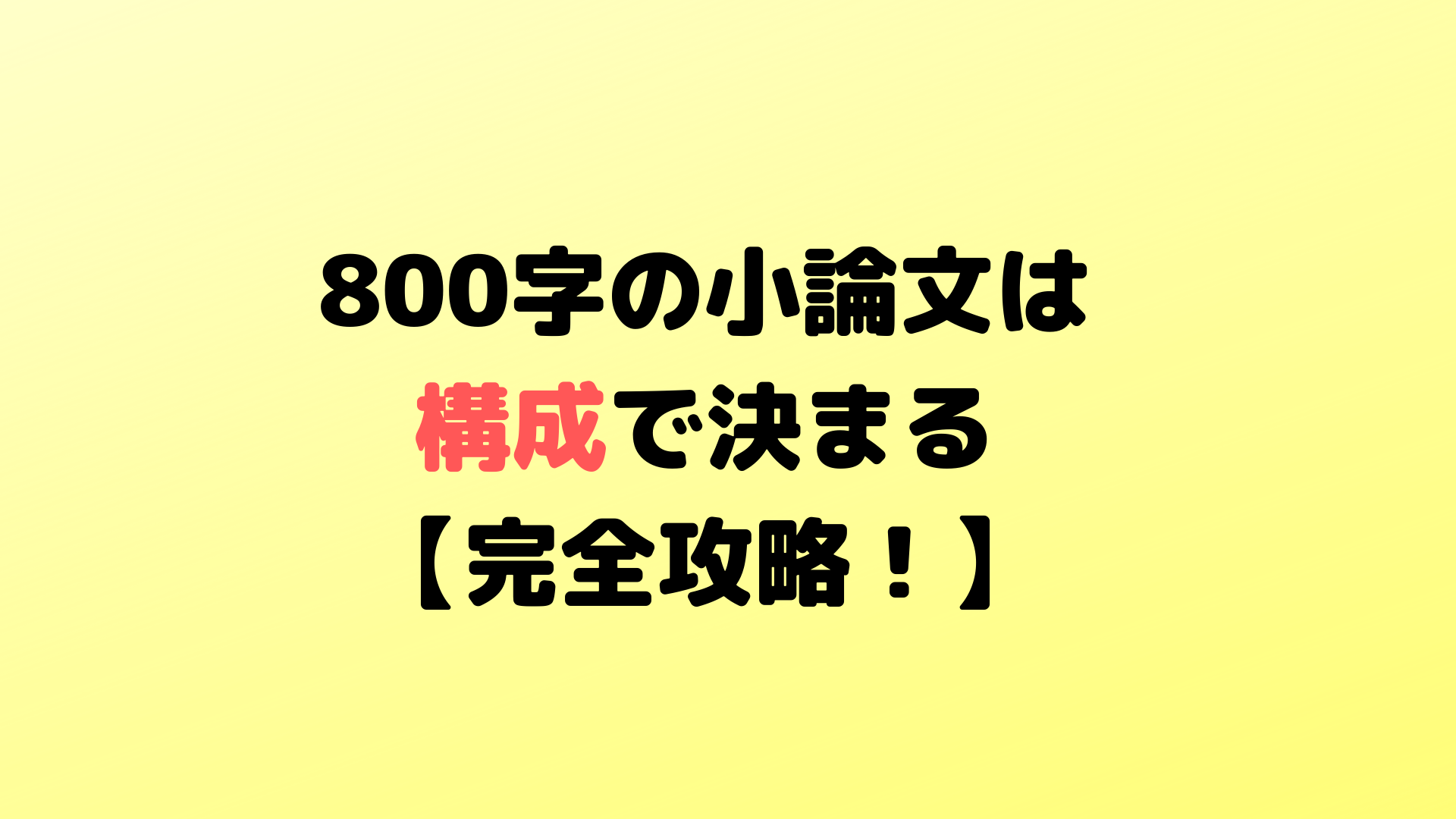
書き方を身に着けたい方は参考にしてください。
【テーマの振り返り】
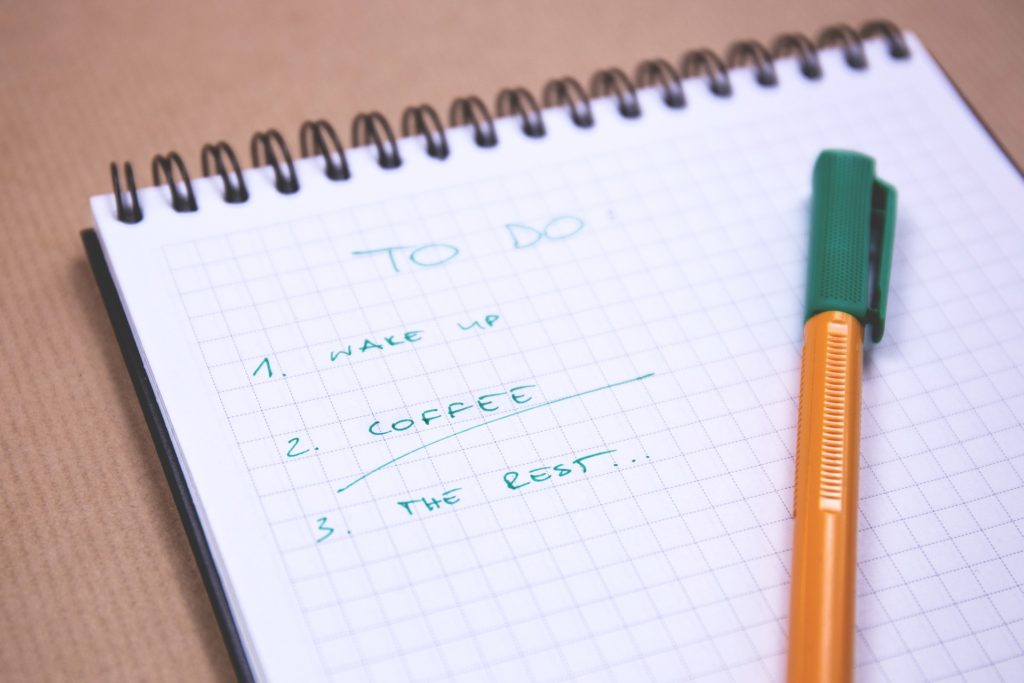
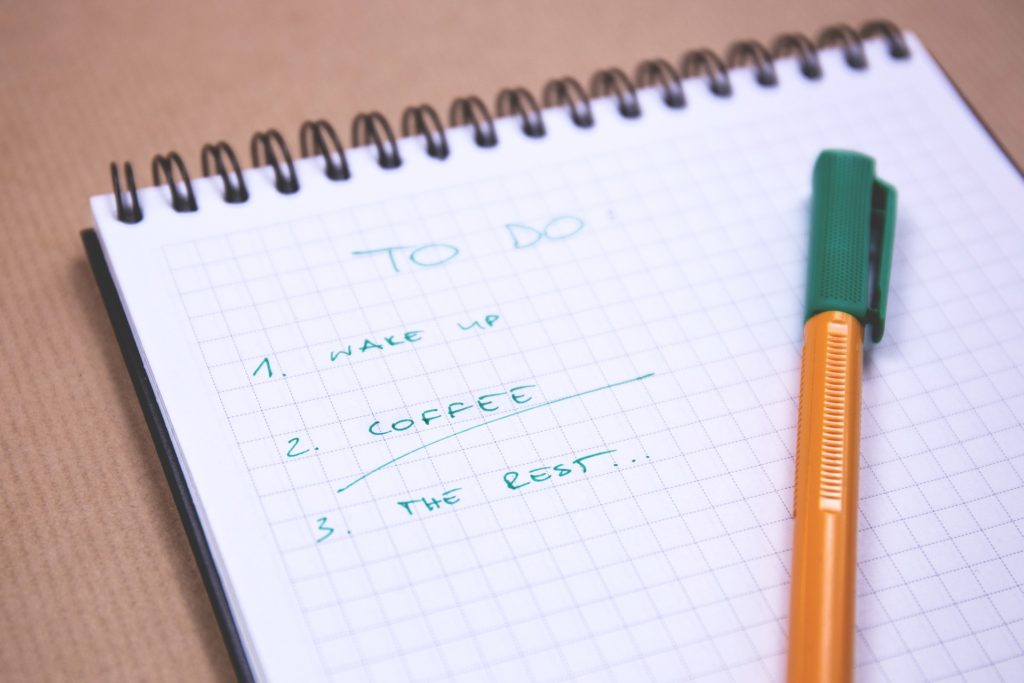
同性婚の問題は、なかなか解決される感じがないですよね。
なぜ問題が解決されないかと言うと、これは個人的な感覚ですが、問題に関わる人の実数が少なく見えているからだと思います。
どんな問題にも言えることですが、実数が少なく見えたり危機感が感じられなかったりすると、周りの人間も本気で取り組もうと思いません。
どんな方法でも構わないので、「同性婚の問題で困っている人がこれだけいる」ということをもっと公にできれば、議論は進展すると思います。もちろん、僕が今述べたことを実行するのはめちゃくちゃ大変です。一般的な価値観との戦争だと僕は思っています。
また、この機会にぜひあなたも同性婚の問題を調べて、自分なりに考察してみてください。主体的に取り組む姿勢が、あなたの思考力を磨いていきます。
では、以上となります。
小論文の作成頑張ってください!
●関連記事


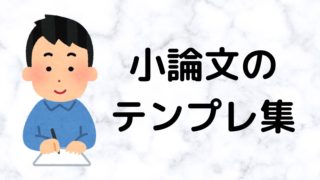
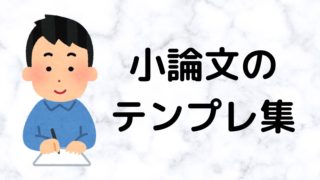


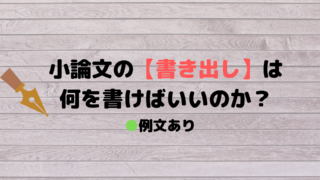
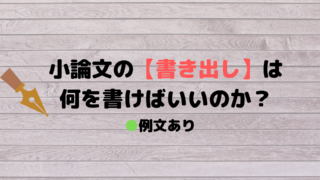
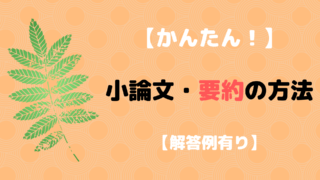
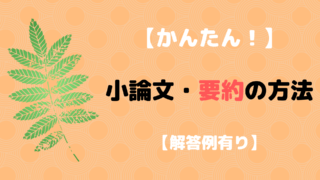
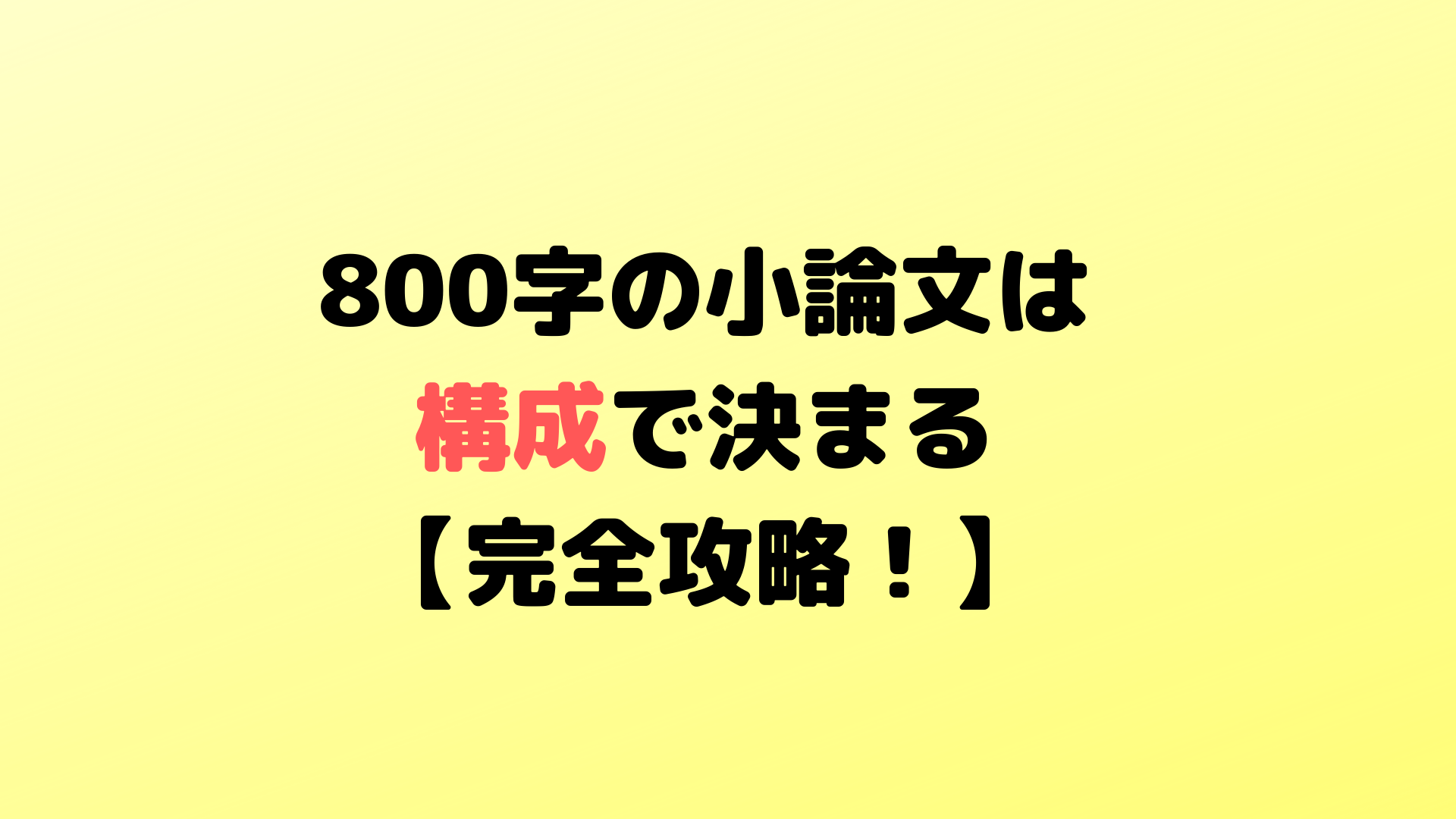
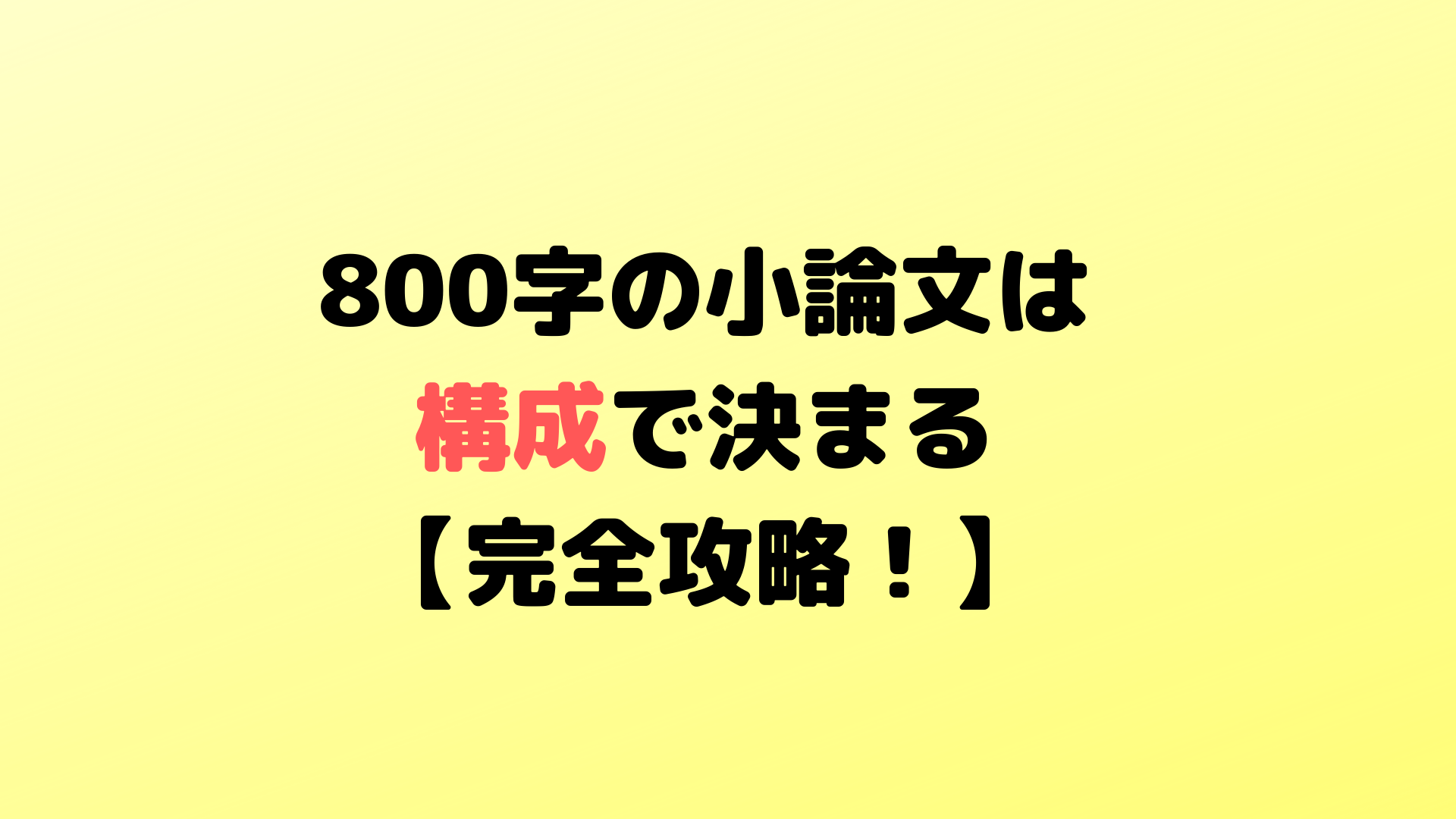
参考文献
渋谷区HP:https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/kurashi/psinfo_202301.pdf(パートナーシップ制度の利用者数)