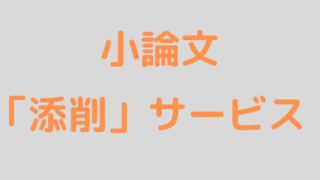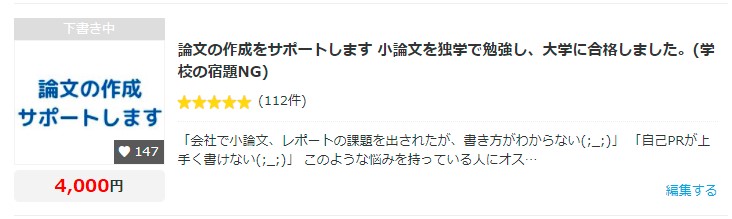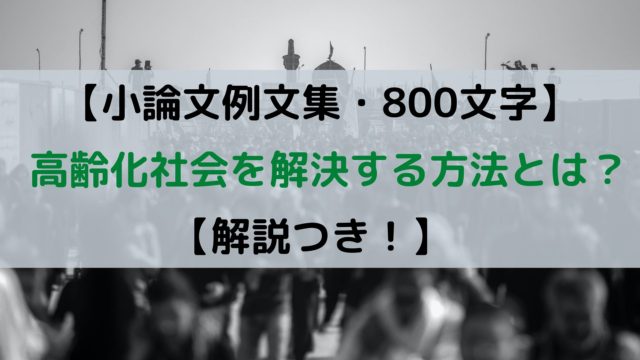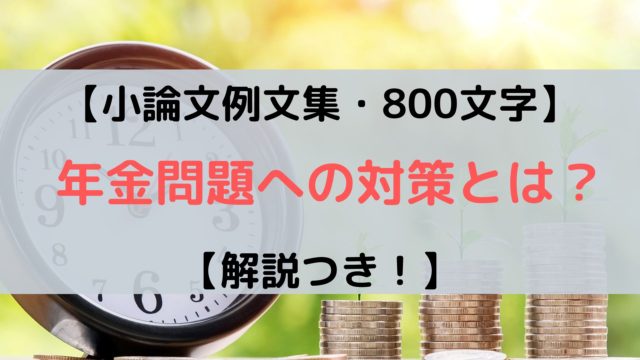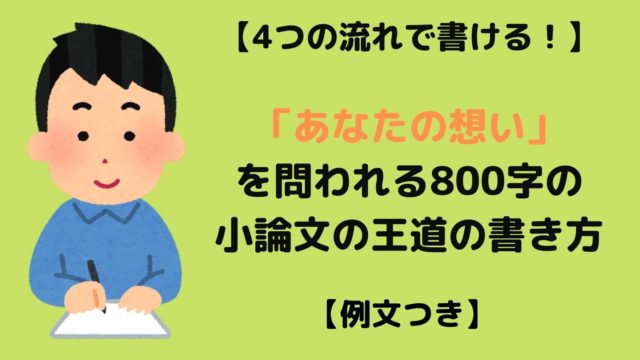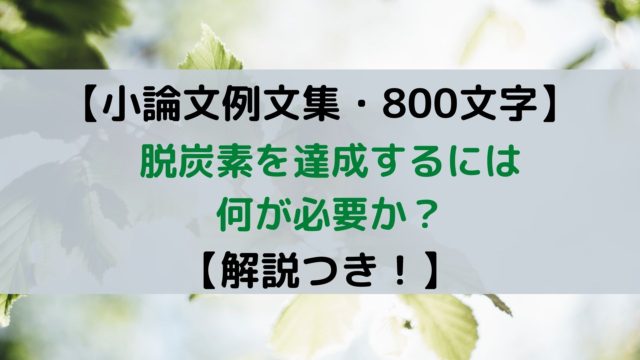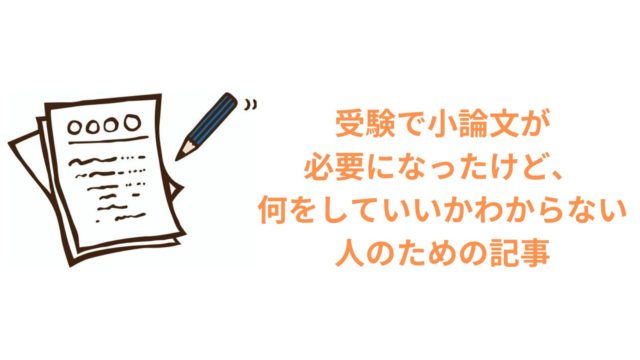・「看護観が小論文で出題された時の対処法を知りたい」
こんにちは、TKです。
私は小論文の書き方を「たった1冊」の本だけで身につけました。
実際にその小論文を利用して、大学に合格したという実績を持っています。
今回の記事では、看護観が小論文で出題された時の対処法を解説します。
そもそも看護観とは?
看護業界を目指す人なら、絶対に持っておくべき看護観。
でも看護観って言葉はあいまいで、定義がよくわからないですよね?
看護観を文章化すると「あなたが思う適切な看護」と言い換えられます。
少しはイメージしやすくなったでしょうか。
看護観は「小論文」と「面接」で頻出する超重要テーマです。
看護医療業界を目指す方はぜひ目を通してください。
小論文で看護観について書く前に、押さえるべき1つのポイント【主観的に書こう】

看護観について書く前に押さえるべき1つのポイントがあります。
それは「主観的に書く」ということです。
基本的に小論文というのは「客観的事実」を軸に書くことが一般的です。
しかし中には「主観的」に書くことが求められるテーマがあります。
それは「あなた自身のこと」について聞いているテーマです。
先ほど、看護観とは「あなたが思う適切な看護」と説明しました。
「」のなかを見ると、あなたという文字がありますね。
このように、あなたが軸になっているテーマは主観的に書くことが求められます。
なので周りの意見は気にせず、自分なりの看護感を表現してください。
小論文で看護観を書く時のオススメ構成

看護観について小論文を書く場合、以下のような構成で書くのが妥当です。
- 序論(あなたなりの看護観を定義づける)
- 本論(看護観が形成された体験談)
- 結論(看護観を仕事でどのように活かしていくか)
この構成で小論文を書けば「看護観が形成された背景と、それをどう仕事に活かしていけるか」をわかりやすく伝えることができますね。
ぜひ今回の構成を意識して、小論文を書いてみてください!
もし小論文の添削や代行が必要な場合は以下のページから受け付けております。
それでは、小論文の勉強頑張ってください!
今回の記事は以上になります!
「今回の記事が参考になった方」や「ブログを一緒に継続していきたい」という方は、ぜひツイッターのフォローをお願いします!
最後まで見ていただき、ありがとうございました!