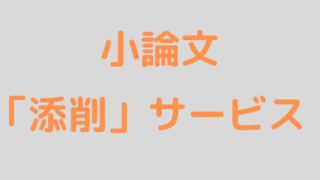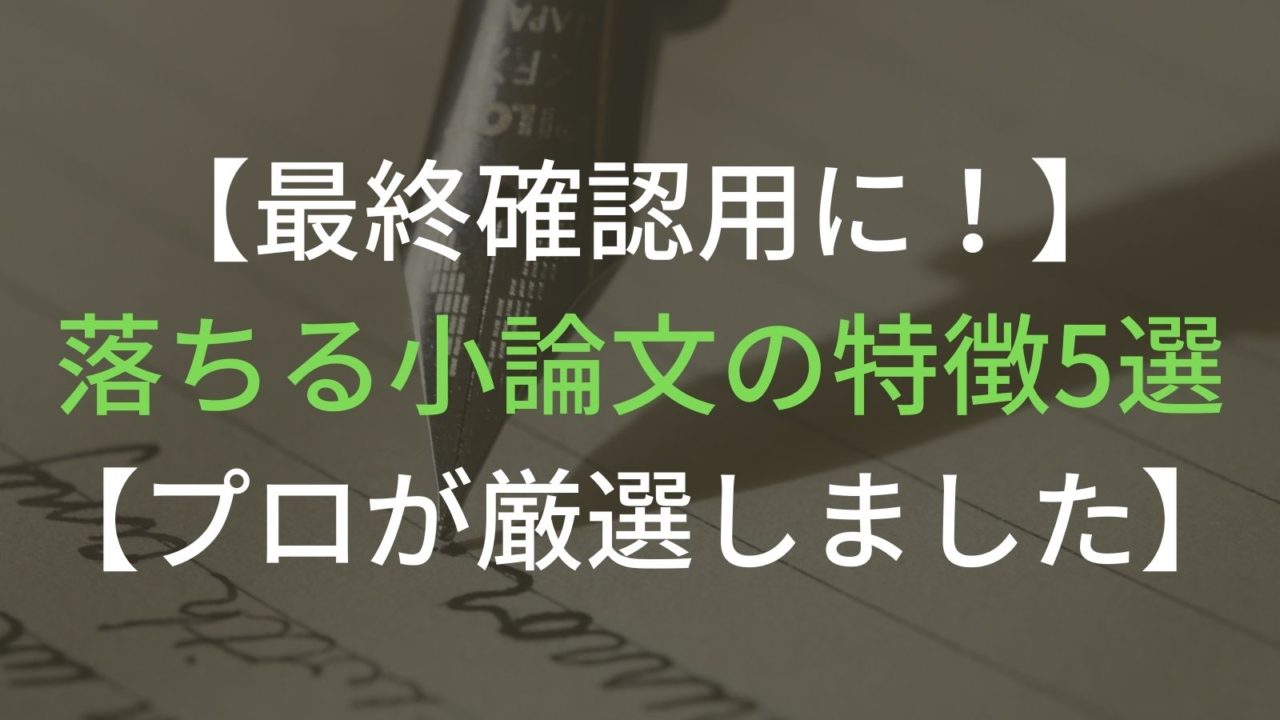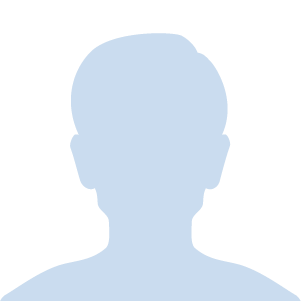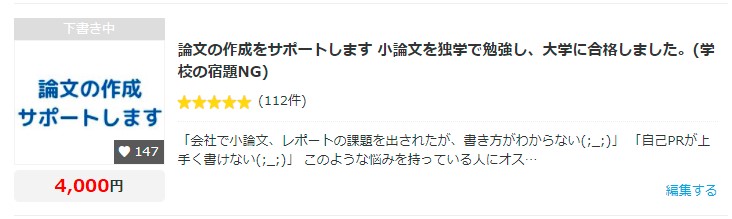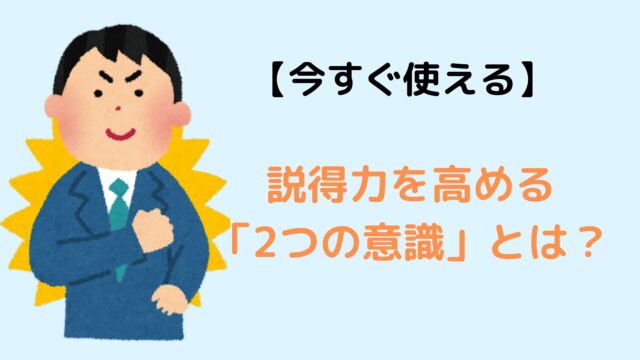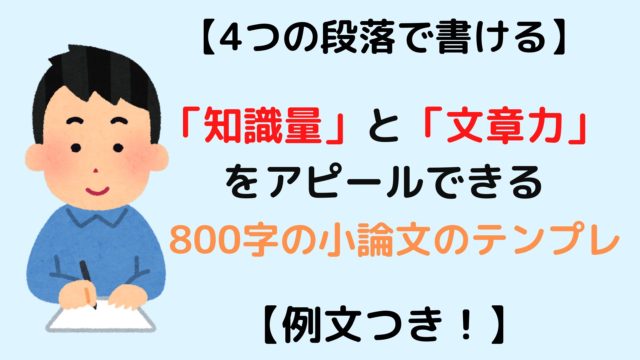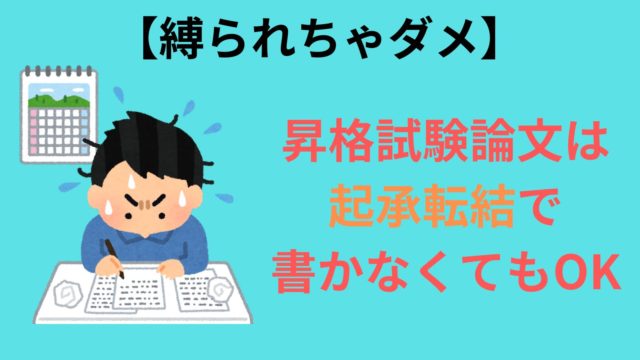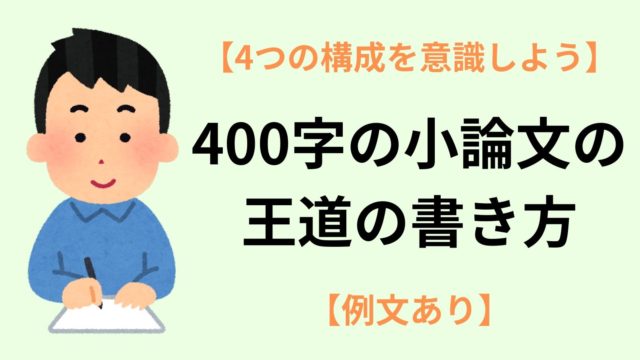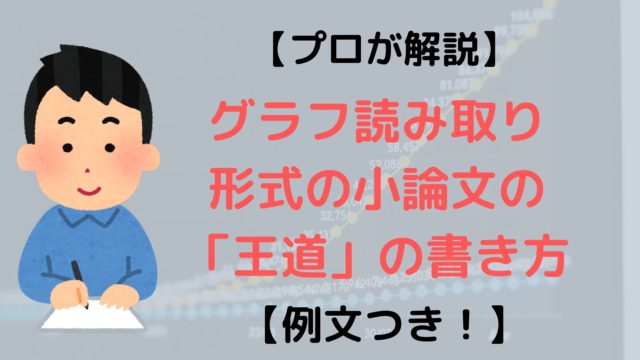- 小論文を書いてみたけど、これでいいのかよくわからない…
この記事は、こんな悩みを持った方に向けて書かれています。
まずは軽く、僕の自己紹介をさせてください。
- 小論文を独学で習得
- 小論文を使って大学に合格
- 小論文の書き方を教える当ブログを作成
- 昇格試験論文のサポートをこなした経験あり→小論文代行サービス
- 某省庁のエントリーシートの代行をこなした経験あり→小論文代行サービス
- 論文関連のYoutube動画を作成↓
独学の体験談を詳しく知りたい方は、以下のページを参照してください。
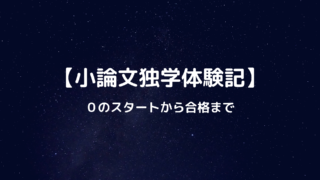
就活・昇格・講義など、あらゆる場面で求められる小論文。
書いてはみたものの、これで合格点が取れるのかどうかが全くわからないというのが本音ですよね。
そこで今回は、落ちる小論文の特徴5選をお教えします。
今回の記事を最後まで見ていただければ、少なくとも、絶対に落ちる小論文は避けることができます。
最終確認用にぜひご活用下さい。
【最終確認用に!】落ちる小論文の特徴5選【プロが厳選しました】

では、淡々と落ちる小論文の特徴を書いていきます。
課題の問に答えていない
圧倒的に落ちる可能性が高いのが、「課題の問に答えていないこと」ですね。
と思われたかもしれませんが、意外と問に答えていない人はいるんですよ。
僕は仕事柄多くの方の論文を見てきましたが、そもそも問に答えていないような論文をお見かけしたことがあります。
当然ですが、そのような論文は99%落ちます。
例えば、お題:ネット上で気軽にコミュニケーションをとるのに便利なSNS。このSNSはわたし達の生活に便利にする一方、様々な社会問題のきっかけになることもある。わたし達はSNSをどのように利用していくべきか?あなたの考えを800字以内でまとめなさい。という問いがあったとしますよね。
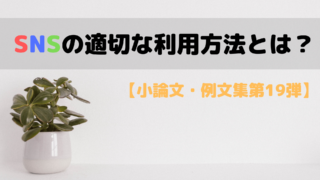
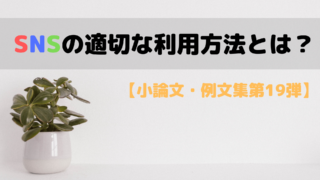
この課題には、「SNSをどのように利用していくべきか?」という問いが含まれていますよね。
したがって、SNSをどのように利用していくべきかを書く必要があるのは明白です。
しかし、意外とこういう明確な問に答えない人がます。
例えば「終始SNSの問題について書いてしまって、明確な問に答えないまま終わる」みたいな感じですね。
まず一度、課題に含まれている問と自分の小論文を照らし合わせてみてください。
ちゃんと確認してみると、意外と問への答えが抜けていることがあります。
言いたいことがよくわからない
次に多いのが、「言いたいことがよくわからない」という小論文ですね。
小論文はだいたい1,000字前後と長い文章を書かされますから、その中で言いたいことをわかりやすく表現するのが難しいのは理解できます。
おそらく初めて小論文を書いた方は、
となってしまったと思います。
では、なぜ言いたいことがよくわからない文章になってしまうのか?
主な原因として考えられるのが、「構成が考えられていないから」ということです。
小論文は長文ですから、構成を考えて書かないと必然的にめちゃくちゃな文章になります。
したがって、小論文を書く際には小見出しを作るなどして、ある程度構成を考えてから書き始めることをおすすめします。
具体的な構成の作り方は以下のページで解説していますので、ぜひ参考にして下さい。
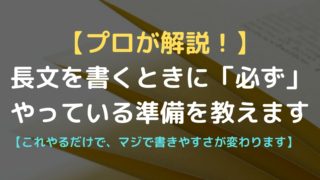
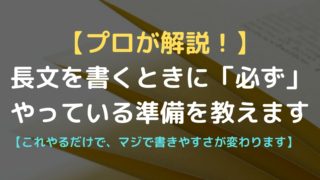
曖昧な表現が多い
長文を書いているとついやりがちなのが、「曖昧な表現を多くしてしまうこと」です。
なぜ曖昧な表現が多くなるのか?原因は以下2つと考えられます。
- 文字数を稼ぐため
- 自分が理解できていない内容を書いているため
まず言っておきますが、以上2つの原因を元にして曖昧な文章を書くと、かなりの確率で読み手にバレます。
「あっ、この表現は文字数を稼ぐために書いてるな」とか「これ、自分でも書いていること理解していないな」みたいに思うことはよくあります。
さっきから言っている「曖昧な表現」をもっと具体的に言うならば、「不要な副詞」のことだと思ってください。
「不要な副詞」とは、例えば以下のような言葉のことです。
- 全体的な
- しっかりとした
- 大きな
- すごく
もちろん、上記の副詞を使うことには問題はありません。
問題なのは、上記のような副詞を「多様すること」です。
副詞は多様されれば多様されるほど、文章は曖昧になっていきます。
不必要に副詞を使っていないかを、必ず最後に確認しておきましょう。
難しい言葉が多い
小論文を書いていると、見た目をカッコよくするために難しい言葉を多様する人がいますが、それはやめてください。
小論文は「読み手に主張をわかりやすく表現する資料」ですから、言葉は簡単であればあるほど良いです。
ここで言う難しい言葉とは、以下のような言葉です。
- 一般的ではない専門用語→例:デシャップ
- 一般的ではない横文字→例:アグリーですね
テレビで「アグリーですね」と言っている人がいましたけど、あれは視聴者に全く寄り添っていないと言えます。
「アグリーですね」じゃなくて、「同意できますね」と言えばいいのです。
ここで言いたいのは、「難しい言葉を多用するのはあなたの自己満足」ということです。
読み手は難しい言葉など一切求めていません。
誰が読んでもわかるような言葉遣いを心掛けて下さい。
読点(、)が多い
長文を書き慣れていないと、ついつい読点(、)を多用してしまうものです。
ただ、読点が多くなるとめちゃくちゃ読み辛い文章になります。
例として、以下の文章をご覧ください。
テレビで「アグリーですね」と言っている人がいましたけど、あれは視聴者に全く寄り添っていないと言えまして、この場合、「アグリーですね」じゃなくて、「同意できますね」と言えばよくて、つまりここで言いたいのは、「難しい言葉を多用するのはあなたの自己満足」ということです。
はい、いかがでしょうか。
先述した文章を読点でつないでみましたが、めちゃくちゃ読み辛いですよね。
したがって文章を書く際には、「1つの文に読点は3つまで」という意識を持つことをおすすめします。
もし読点が4つ以上になっていれば、それは別々の文に分解したほうがいいです。
意外と読点は多用しがちになるので、注意しておきましょう。
まとめ
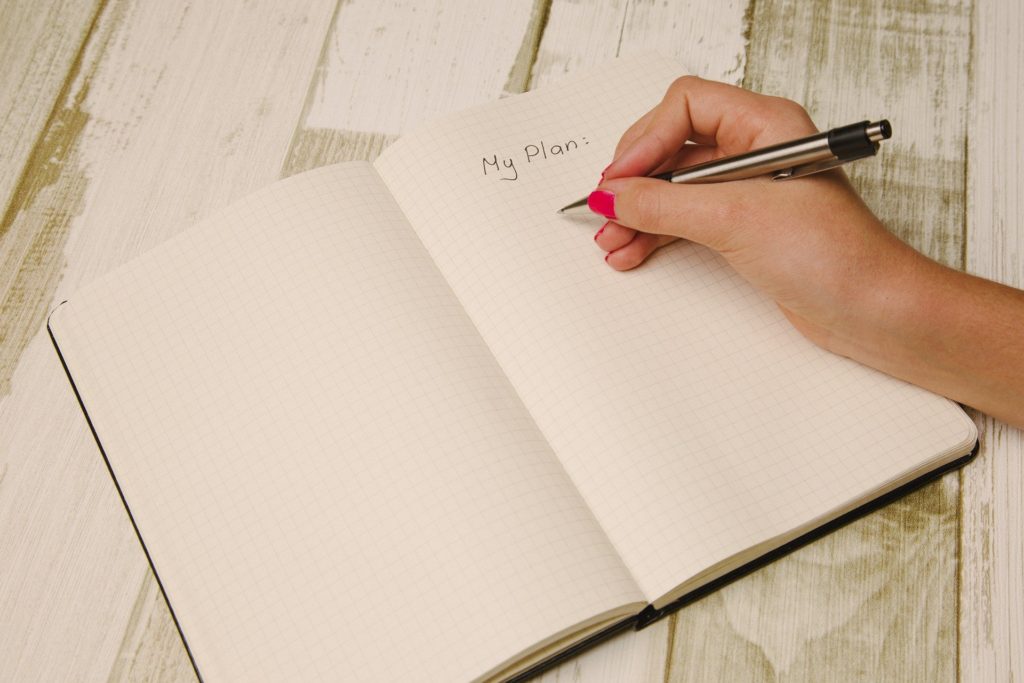
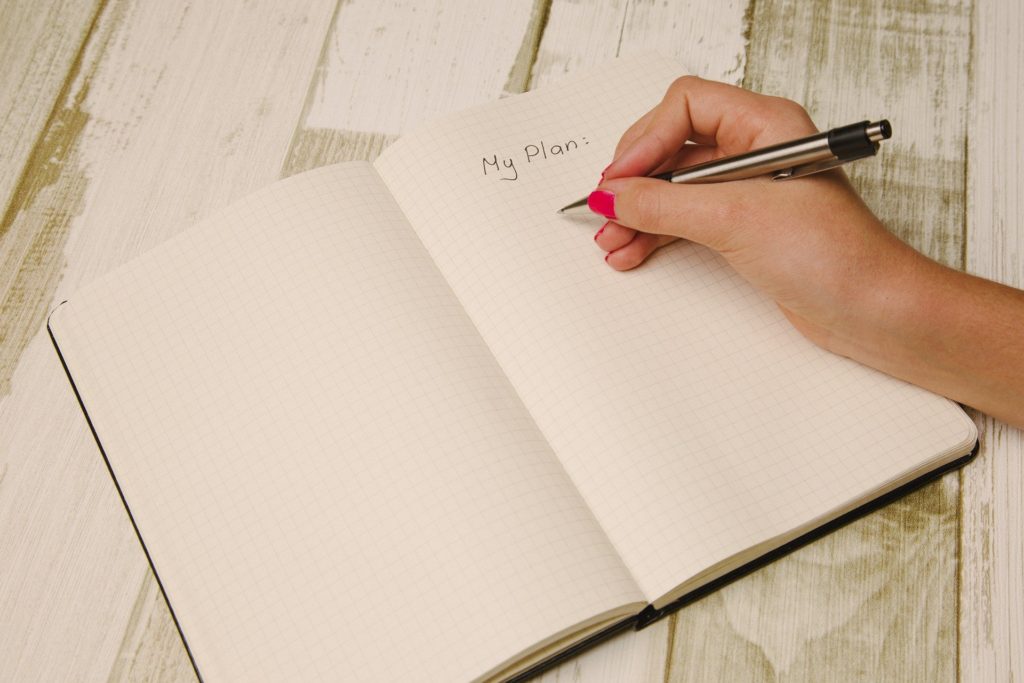
今回は落ちる小論文の特徴5選として、以下5つの特徴を解説しました。
- 課題の問に答えていない
- 言いたいことがよくわからない
- 曖昧な表現が多い
- 難しい言葉が多い
- 読点(、)が多い
この5つの特徴を無くしていくだけでも、小論文の読みやすさは格段に向上します。
最終確認として、ぜひ参考にして下さい
では、以上となります。
小論文の作成、頑張ってください!