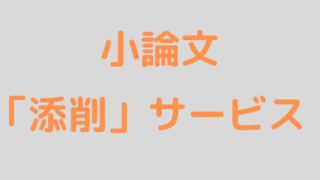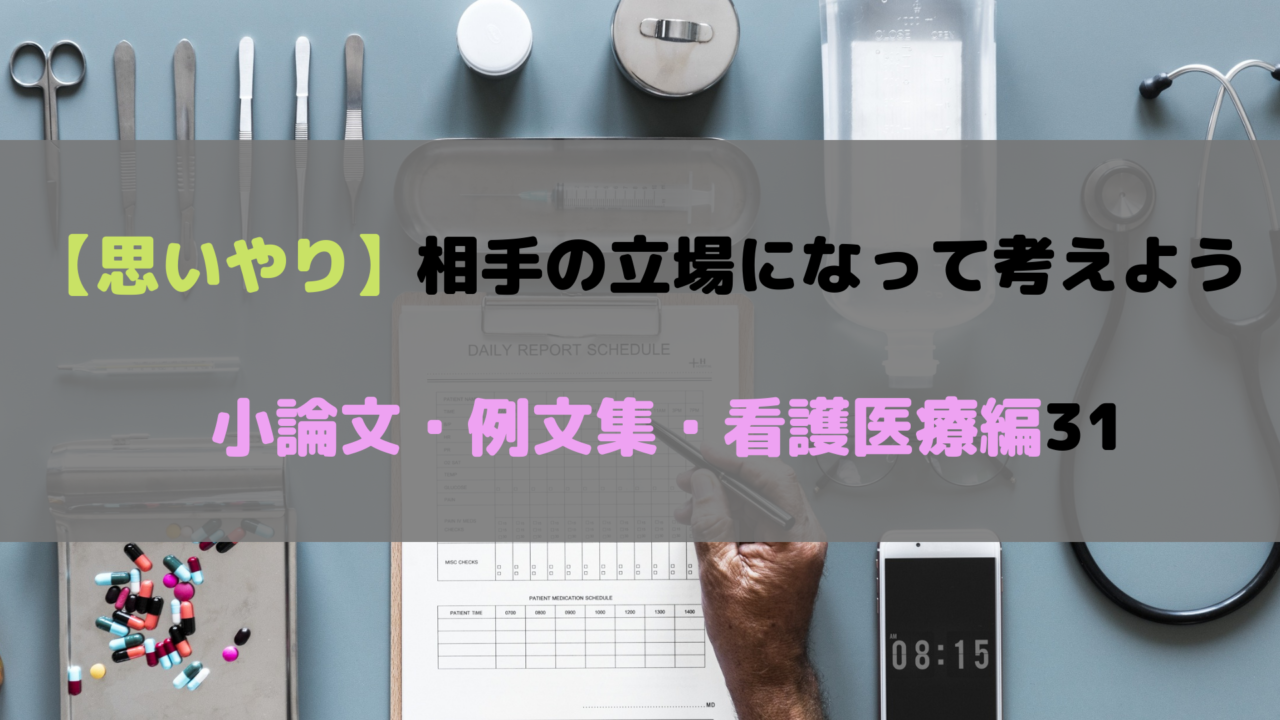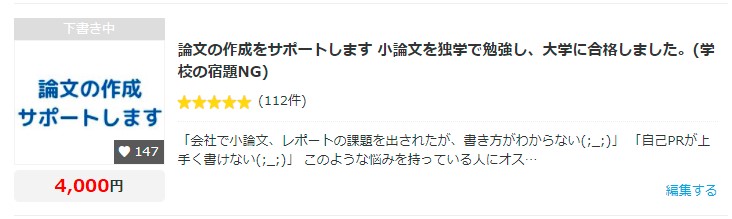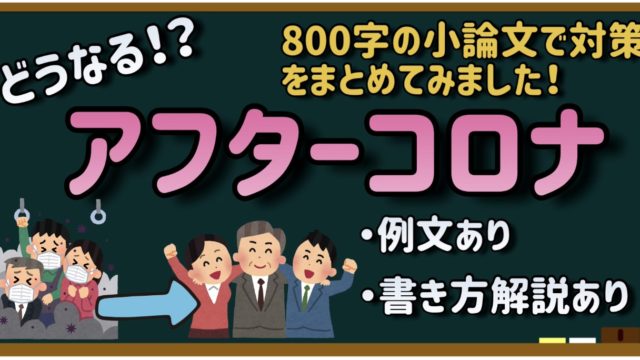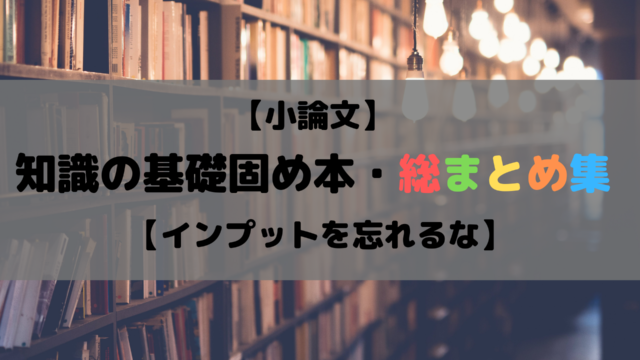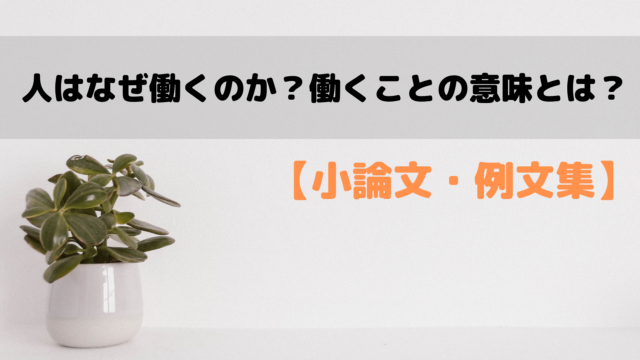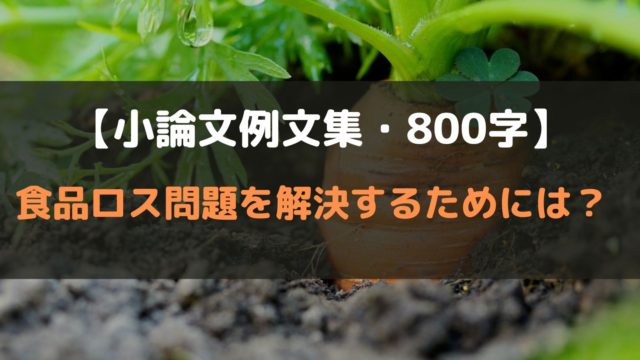・「思いやりについて考察したい人」
・「受験や就職で小論文が必要になった人」
こんにちは!
私は小論文の書き方を「独学」で身につけました。
実際にその小論文を利用して「大学に合格」という実績を持っています。
今回の記事は、小論文・例文集第31弾です。
お題はこちら。
お題:あなたにとって「思いやり」とは何か?800字以内でまとめなさい。

思いやりって、まあまあ抽象的な表現ですよね。
このように「定義が曖昧な言葉」をどのように考えているか?
小論文で問われることが頻繁にあります。
あなたにとって「思いやり」とはなんですか?
今回の記事では「思いやり」を軸に小論文を書いていきます。
看護医療業界を目指す人は、ぜひ押さえてほしい記事です!
それではご覧ください。
【思いやり】相手の立場になって考えよう【小論文・例文集第31弾・看護医療編】
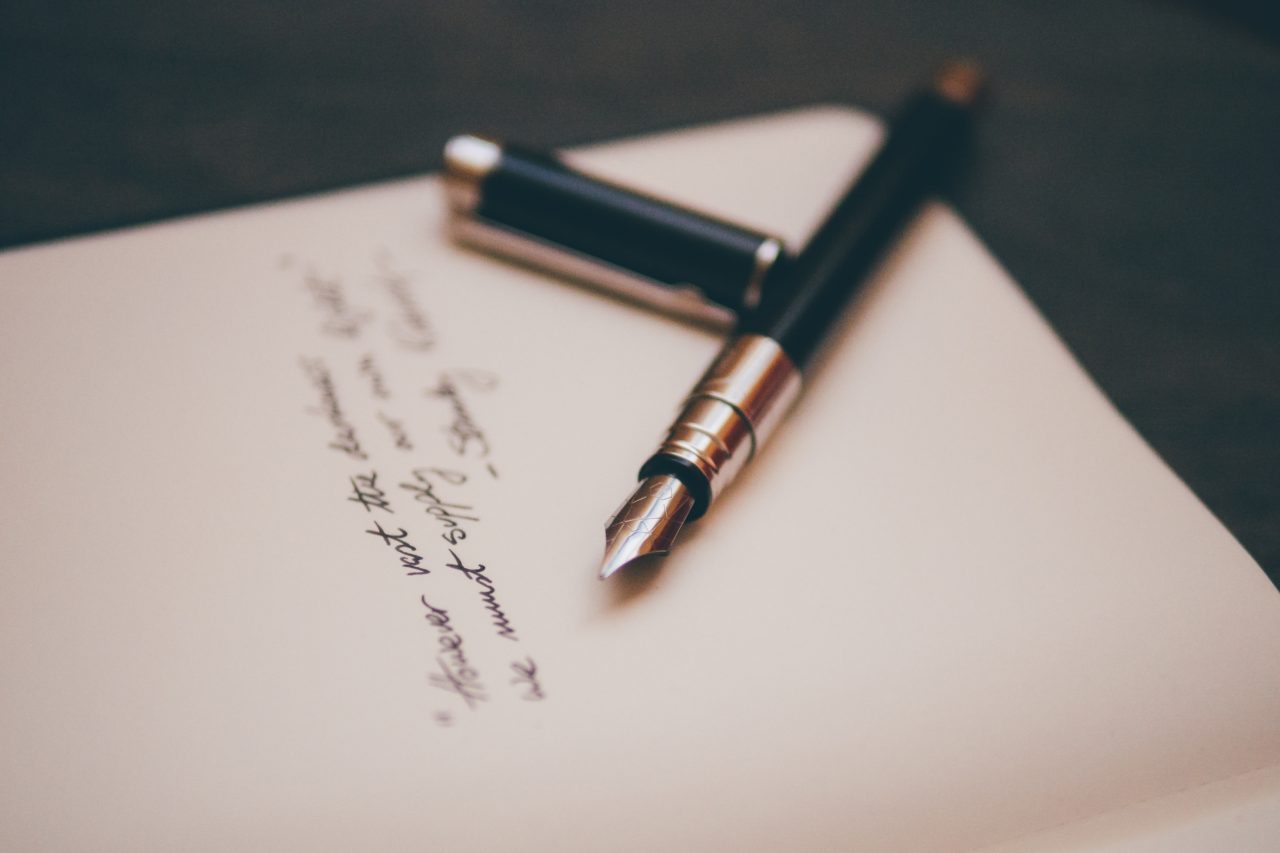
お題:あなたにとって「思いやり」とは何か?800字以内でまとめなさい。
① 思いやりとは非常にあやふやな言葉だ。簡単に言ってしまえば「相手の為になることをする」と言えるだろうか。しかし、相手の為になることが具体的にどういった行動か?それを明確に言葉にするためには、思いやりの意味を自分で考えて実行することが必要になる。以下では、自分の経験を交えつつ、思いやりの意味について論じていく。
② 私は、思いやりとは「相手の立場になって、物事を考える努力をすること」だと考えている。理由は、相手の立場になってみないと、コストや問題点に気づくことができないからだ。このような考えを持った要因は、車で友人を迎えに行った経緯からきている。友人の仕事が終わった後に、私が車で職場まで迎えに行くことが頻繁にあった。車を出すというのは、ガソリン代も掛かるし、運転する私の労力も発生している。しかし友人は私に対する感謝の気持ちはほとんどなかった。車を持っているのだから、車を出すのは当たり前と思っていたらしい。友人は車を所持していなかったので、車を出すコストや労力を理解できなかったのだ。当然私は途中から嫌気が差すようになり、車を出す頻度は大幅に減った。
③ では、相手の立場になって考えるためにはどのような思考が必要か?それは自分の感情や答えを一切持たず、理屈だけで考えることである。友人だからとか、親だからという理由で考えることをやめると、どれだけ自分が世話になっているかを理解することができない。事実に基づいた考えだけを持てば、相手が抱えているコストや問題点に気づくことができる。その結果、相手のためになにができるか?という答えを見つけることができるのだ。
④ 思いやりを持つというのは、自分の感情を一切持たず、理屈のみで相手の立場を考えることだ。そうすることによって、本当の意味で相手の立場になることができ、いわゆる「思いやりのある行動」がとれると私は考える。
例文解説

通読お疲れさまです!
「相手の立場になって、物事を考える努力をすることが思いやり」という主張を軸に小論文を書いてみました!
この小論文は以下4つのブロックで構成されています。
- テーマ解説
- 主張(相手の立場になって、物事を考える努力をすることが思いやり)
- 主張の深堀り(理屈のみで考えることで、本当の意味で相手の立場になれる)
- まとめ
それぞれのブロックを簡単に解説していきますね。
①テーマ解説
どのようなことについて論じていくのかを明確にしました。
論じる内容を簡単に示しておくことで、読み手の負担を減らすことができますね。
これも「思いやり」の一種です。
②主張
自分の主張を、体験談を交えながら書いたのがポイントですね。
体験談を交えることで、主張の説得力が増します。
よく使われるテクニックなので覚えておいてくださいね。
③主張の深堀り
②で述べた主張を、より具体的に書きました。
「相手の立場になって、物事を考える努力をすること」って具体的にどうすればいいの?という疑問が読み手に生じていると考えて、深堀りしたのです。
詳細な記述は「深い思考を持っている」ことをアピールできるので、積極的に入れていきましょう。
④まとめ
最後は今まで述べてきたことを、表現を変えて短くしただけです。
②と③の重要な部分だけを抜き出して伝えれば十分でしょう。
オマケとして、今回と違う構成の小論文を詳細に解説したページを載せておきますので、参考にしてください。↓
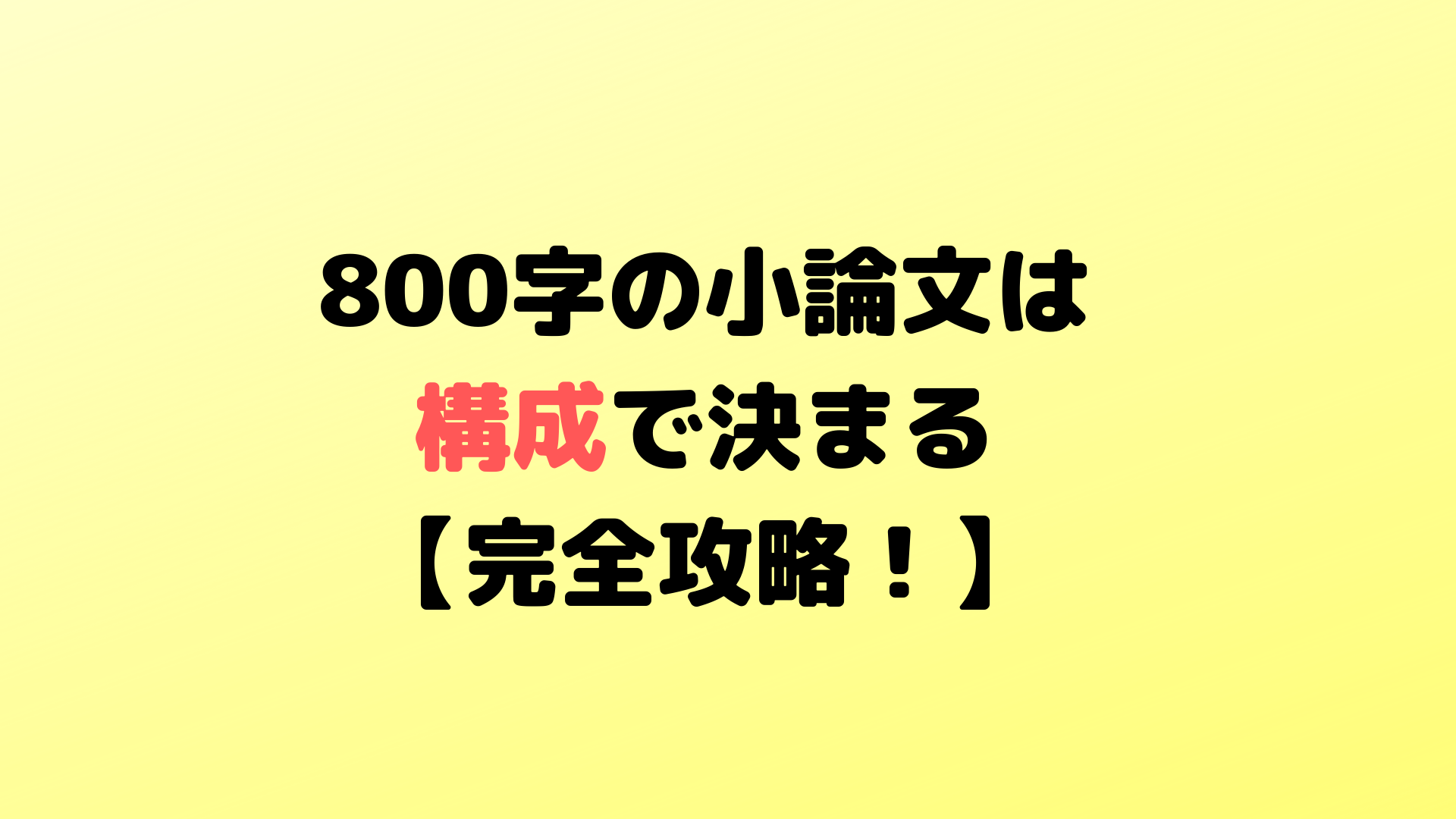
「他の例文からも学びたい!」という人は下記のページへ。
複数のお題から学ぶことであなたの小論文の幅が広がり、どんなテーマにも対応できる力が身につきます。
テーマの振り返り、感想
今回のように、曖昧な言葉について考えさせるテーマが小論文では出題されることがあります。
もし普段から考えていなかったテーマが出た時、結構焦ると思います。
そうならないためにも、様々なテーマで小論文を書く訓練を積んでおいてください!
その積み重ねが、試験でも絶対に活きてくるはずです。
今回の記事は以上になります!
最後まで見ていただき、ありがとうございました!