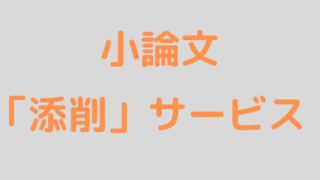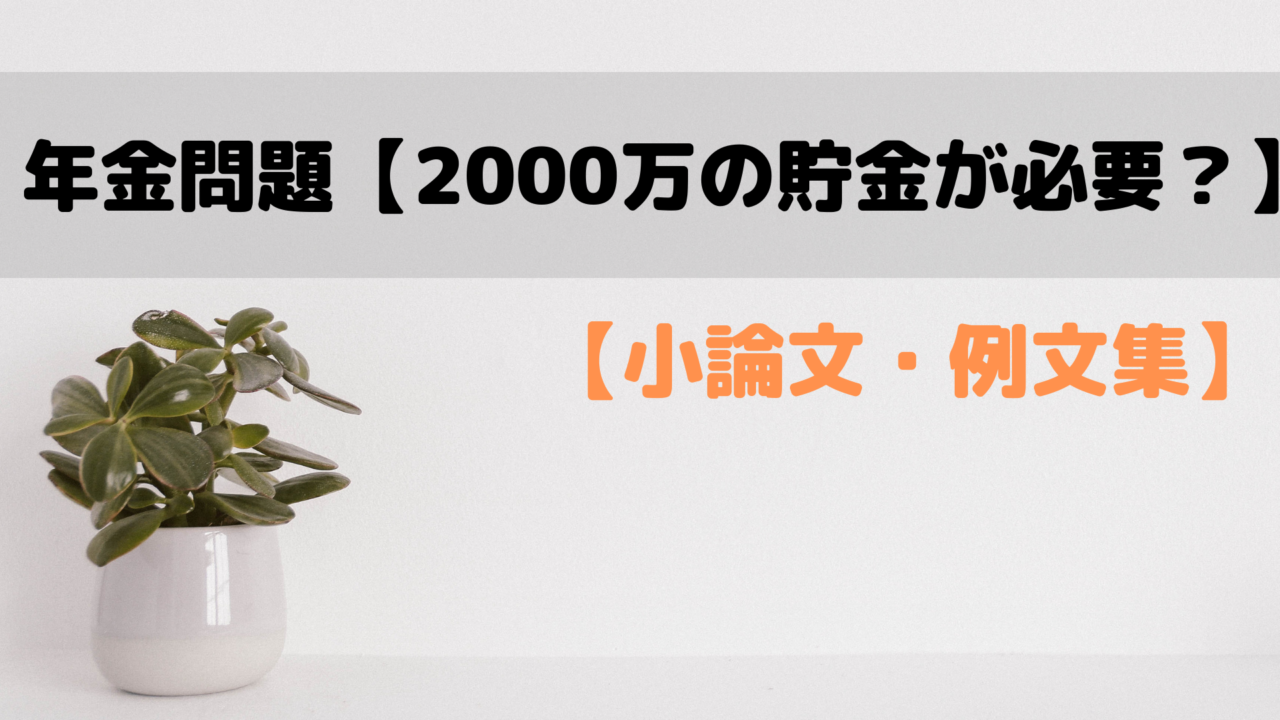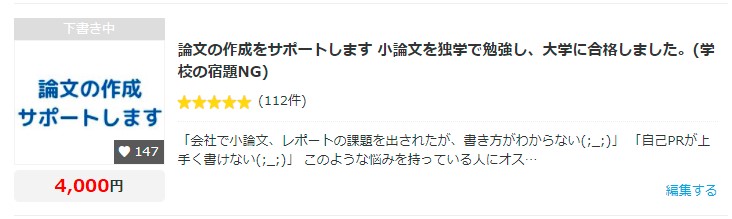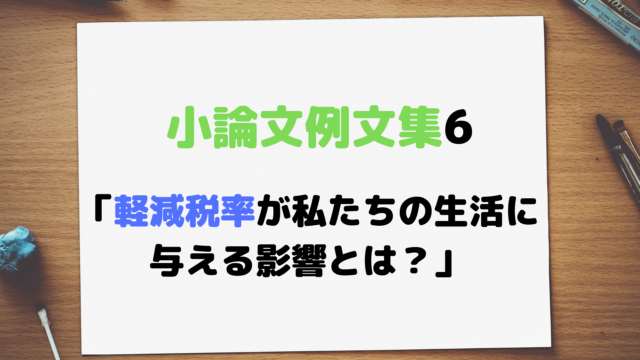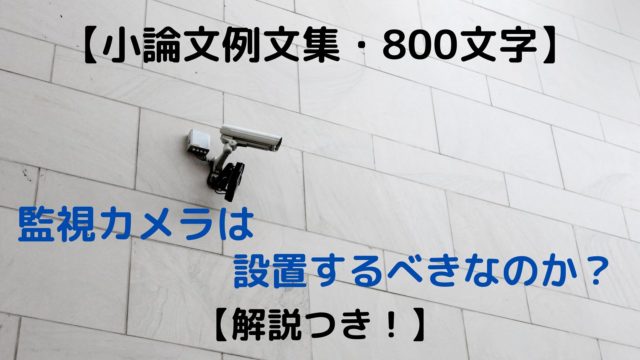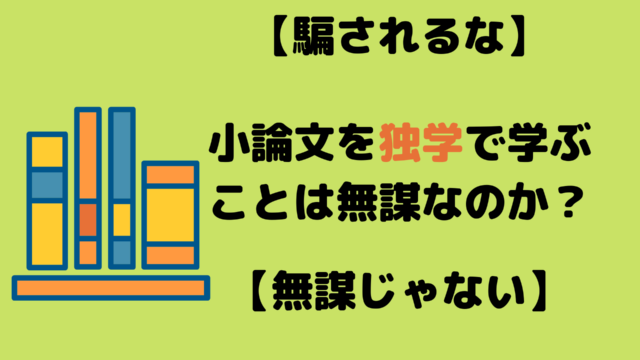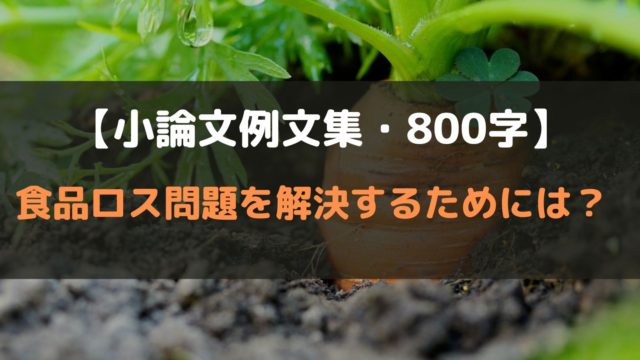・「年金問題について考察したい」
・「小論文が受験や就職活動で必要になった」
こんにちは!TKです。
私は小論文の書き方を「独学」で身につけました。
実際にその小論文を利用して「大学に合格した」という実績を持っています。
今回の記事は、小論文・例文集です。
お題はこちら。
お題:2019年6月3日、金融庁から老後の資産として「2000万円」を個人で用意する必要があると発表された。老後の生活を年金に頼ることが難しい現役世代は、豊かな老後をおくるためにどのような行動をとるべきか?あなたの意見を800字以内で述べなさい。

年金問題とは?
将来、年金の受取り額が減少したり、受給開始年齢が引き上げられたりするのでは?という懸念のこと。
金融庁の発表には驚かされましたよね。
遠回しに「年金制度は崩壊した」と言われたようなものです。
こうなってしまったら、国に頼るのではなく、個人で老後の生活を支えていく方法を考える必要がありますね。
あなたは年金問題に対してどのような意見を持っていますか?
今回の記事では「年金問題」について小論文を書いていきます。
それではご覧ください。
【小論文・例文集】年金問題【2000万の貯金が必要?】
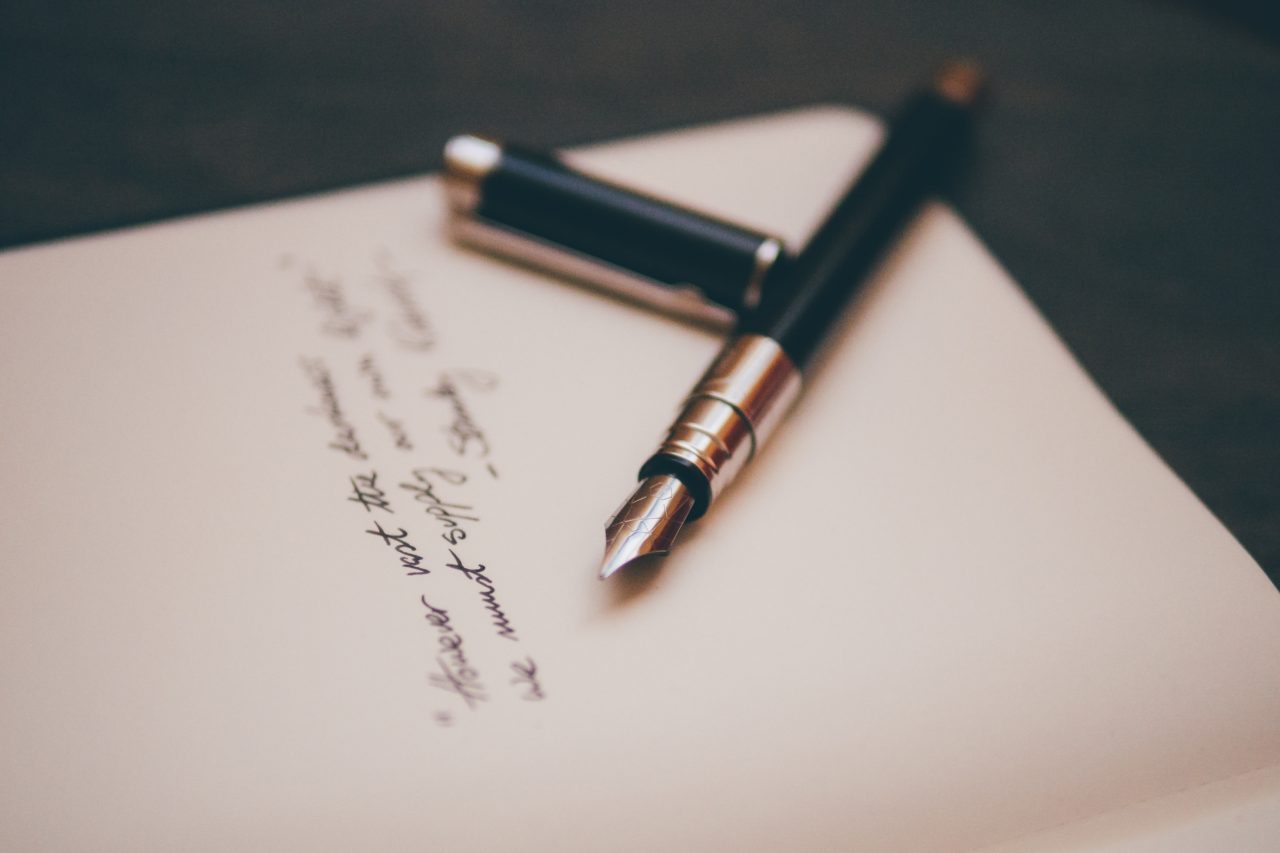
お題:2019年6月3日、金融庁から老後の資産として「2000万円」を個人で用意する必要があると発表された。老後の生活を年金に頼ることが難しい現役世代は、豊かな老後をおくるためにどのような行動をとるべきか?あなたの意見を800字以内で述べなさい。
① 近年、年金問題が深刻化している。金融庁の試算によると、年金とは個別に2000万円の資産が、老後を豊かに過ごすために必要らしい。もう年金だけに頼ればいい時代は終わりを迎えつつあるのだ。金融庁の報告を鑑みて、現役世代はどのような対策を講じるべきだろうか?
② 私は、個人で金融商品に投資をして、資産を築いていくべきだと考える。今までは国から支給される年金である程度の生活を送ることができた。しかし、これから貰える年金は間違いなく減少の一途をたどる。その埋め合わせのために、個人で資産を築かなけらばならない。幸い個人で金融商品を買うハードルはとても低いため、誰でも簡単に購入することができる。もちろん何の知識を持たずに購入することは危険なので、本やネットで勉強する姿勢は必要だ。正しい知識を身につけて投資を行うことで、年金に頼らずとも、豊かな老後を送るための資産を築けるだろう。
③ しかし、「投資にはリスクが伴い、危険なのでやりたくない」との意見もあるだろう。確かに投資にはリスクはつきものだ。しかしその意見は、貯金にはリスクが無いと言ってるいるに等しい。貯金は名目上の金額は変動しないので、リスクが無いように勘違いする。しかし、インフレーションが起これば、実質的な価値は目減りしてしまうのだ。投資は危険で貯金は安全という思考は全く間違っている。そのような考えを持っている人は、まずはお金に関する勉強を始めるべきだ。お金の勉強をすることによって、正しく資産を形成できるようになる。
④ 年金だけで豊かに老後が過ごせる時代は、終わりを迎えようとしている。現役世代は自分で金融商品に投資して、資産を形成していく必要があるだろう。金融商品に抵抗がある人は、まずお金の勉強から始めるべきだ。正しい知識が資産形成の助けになり、老後を豊かに過ごせることにつながると私は考える。
例文解説

通読お疲れさまでした!
「個人で金融商品に投資をして、資産を築いていくべき」という主張を軸に小論文を書いてみました!
この小論文は以下4つのブロックで構成されています。
- テーマ解説と問題提起
- 主張(個人で金融商品に投資をして、資産を築いていくべき)
- 主張に対する批判(投資にはリスクがある→貯金にもリスクはある)
- まとめ
それぞれのブロックを簡単に解説していきますね。
①テーマ解説と問題提起
テーマの解説+問題提起という王道の書き出しです。
非常に使い勝手がいいので、ぜひ身につけてください。
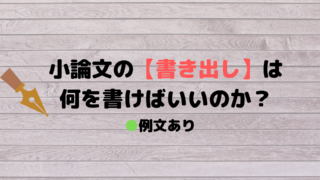
②主張
①の問題提起に対する主張をするという、オーソドックスな書き方です。
主張に加えて「理由」と「具体例」をいれたのがポイントです。
この2点を加えることで、薄っぺらい主張になることを避けられます。
- 理由→貰える年金は減少するから
- 具体例→勉強した上で、金融商品を買うべき
③主張に対する批判
あえて自分の主張に対する批判を書くのは、小論文の鉄板テクニックです。
小論文が議論しているような形式になり、文章に深みが出ます。
しかし最後は、批判に反論して締めるようにしてください
主張に対する批判だけ書いて終わってしまうと、悪い印象を与えたままになってしまいます。
それでは本末転倒ですからね。
- 主張に対する批判→投資にはリスクがある
- 批判に対する反論→貯金にもリスクはある
④まとめ
最後は今まで述べてきたことを、表現を変えて短くしただけです。
②と③の重要な部分だけを抜き出して伝えれば十分でしょう。
オマケとして、今回と同じ構成の小論文を詳細に解説したページを載せておきますので、参考にしてください。↓
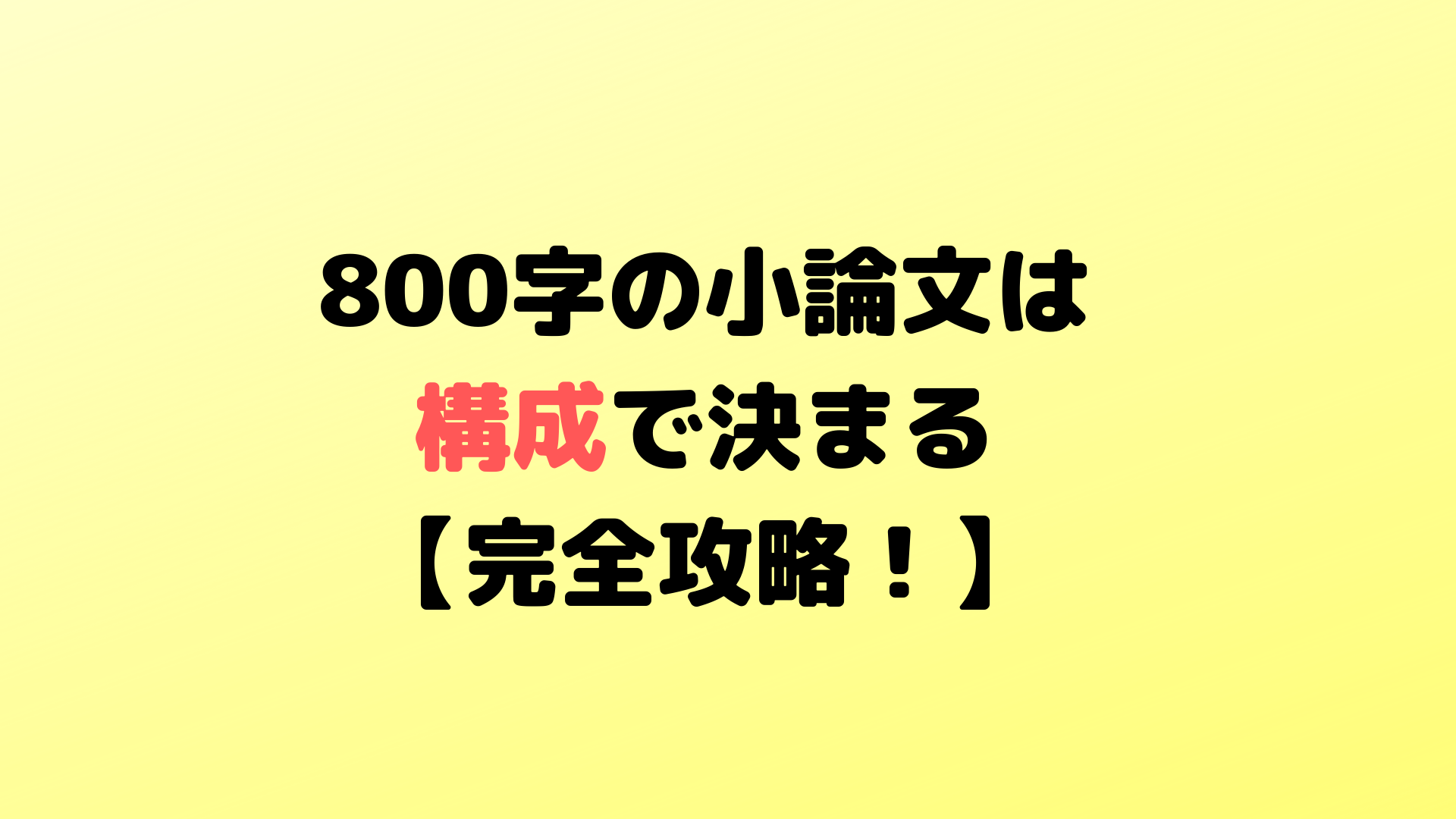
「他の例文からも学びたい!」という人は下記のページへ。
複数のお題から学ぶことであなたの小論文の幅が広がり、どんなテーマにも対応できる力が身につきます。
今回の記事は以上になります!
「今回の記事が参考になった方」や「ブログを一緒に継続していきたい」という方は、ぜひツイッターのフォローをお願いします!
最後まで見ていただき、ありがとうございました!